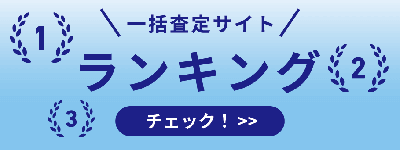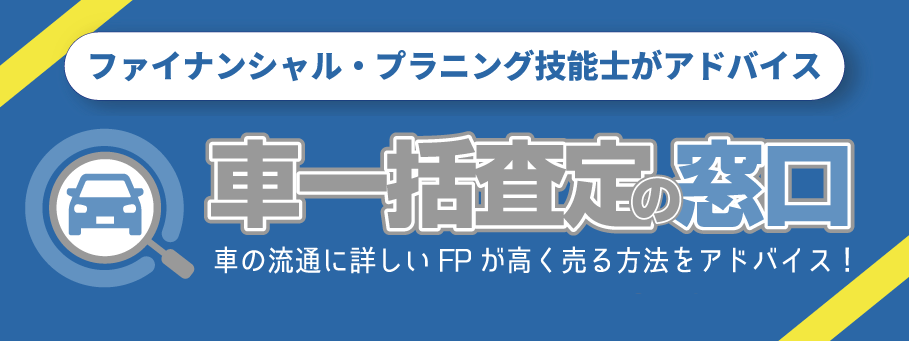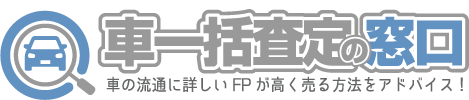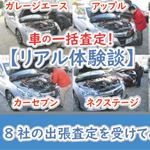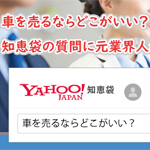- 初めて選んだ車種は?はじめてのマイカーに関する調査を紹介 - 2024年4月15日
- 調べてみたら意外に多い!車や交通にまつわる記念日 - 2024年4月11日
- 完全な自動運転の車に乗りたい人は約6割。意外な理由とは? - 2024年4月8日
BEV(バッテリー式電気自動車)やHEV(ハイブリッド車)など、ガソリンや軽油などの化石燃料を使わない脱炭素社会への適応が、車においても徐々に進んでいます。
(一社)日本自動車販売協会連合会の2020年燃料別新車販売台数(乗用車)調査によると、ガソリン車が55.7%、HEVが37.1%、PHEV(プラグインハイブリッド)が0.59%、BEVを含むEV(電気自動車)が0.59%、ディーゼル車が5.95%、その他0.04%の結果になりました。
この様に販売された乗用車の40%近くが、動力用のバッテリーを搭載してモーターのみ、またはエンジンと併用して駆動する仕組みになっています。
今後はこの動きが加速して、ガソリン車やディーゼル車の比率も、下がっていく傾向にあると言えるでしょう。
今回は、BEVとHEVを中心に、そのメリットやデメリットを交えた特徴を紹介していきます。
電気自動車(EV)の種類は多種多様です
電気自動車(EV)と一言でいっても、最近では、BEVやHEV以外にも、PHEV(プラグインハイブリッド)、FCEV(水素自動車)など、アルファベットの略称で呼ばれる車も増えてきましたので、これら略称の整理を少ししておきましょう。
- EV:電気自動車
- BEV:バッテリー式電気自動車(モーターのみで駆動)
- HV=HEV(※):ハイブリッド車(ガソリンエンジンとモーターで駆動)
- PHV=PHEV(※):プラグインハイブリッド車(外部充電可能なHV車)
- FCV=FCEV(※):水素自動車(水素と酸素で発電してモーターを駆動)
※自動車メーカーによって、アルファベットの略称が異なります
整理すると、一般的にEVまたは電気自動車と呼ばれている車も種類は多種多様なのですが、FCVの一部車種を除いて走行用のモーターを搭載している点では共通していると言えます。
また最近では国産車だけではなく「テスラ」をはじめとして、EV化が進んでいる欧米を中心とした多くの海外メーカー製BEVやPHEV、HEV も輸入販売されていますので、選択肢は年々増えているのが現状です。
BEVの特徴
国内で発売になった頃は、1回の充電で走行可能な距離は160㎞ほどと短かったBEVですが、最近ではカタログ上で400㎞を超えるなど、大幅に航続距離も伸びてきました。
国産車では、「リーフ(日産)」、「Honda e(ホンダ)」などが販売されています。
静かで環境面に優しいのが一番のメリット
モーターのみによる駆動のため騒音がないこと、ガソリンを全く使用しないので、二酸化炭素ガスの発生もないことなど、地球環境にも優しいことが一番のメリットと言えるでしょう。
ランニングコストを抑えられるメリットも
自宅で充電できることに合わせて、夜間に安い電力で充電可能すればランニングコストも削減できる点も、大きなメリットです。
また、国や自治体による補助金や自動車税や重量税の軽減、環境性能割の非課税など、優遇措置が豊富なこともランニングコストを抑えることに一役かっています。
またランニングコストとは言えませんが、リセールバリューが高いことも付け加えておきます。
BEVのデメリットは
ガソリン車やディーゼル車でしたら、ガソリンスタンドで燃料を入れるだけですが、BEVには充電が必要になります。
充電は急速充電もできますが、それでも30分~40分ほど時間もかかりますので、急な外出時などに充電が出来てなくて使用できない可能性があるかも知れません。
また低温での搭載されている電池の性能低下、暖房使用時の電費(燃費)の悪化もデメリットとして挙げられます。
2022年冬の大雪で充電ポートが積雪や凍結の影響で、使用不能に陥ってしまうといったトラブルが、各地で発生しました。
BEV車は、冬場が苦手だと言えるでしょう。
HEV(PHEV含む)の特徴
1997年にトヨタ自動車が「プリウス」を発売したのをきっかけに、国内でのエコカーブームを作り出したのがHEVだと言えるでしょう。
国産車では、「プリウス、アクア(トヨタ)」、「ノートe-POWER(日産)」などが販売されています。
航続可能距離が長いこととランニングコストがメリット
電気のみで駆動するBEVに比べて、ガソリンエンジンを併用しているので、充電スポットを探す必要がなく、長距離のドライブも安心だと言えます。
航続可能距離はBEVよりも長くなることが、実用上にも大きなメリットです。
実燃費でもリッター20㎞を超える車種が多いこと、BEVと同じく各種補助金や税制面での優遇措置は、ランニングコストを抑える点でメリットと言えます。
またBEVと同じく、リセールバリューも高いと言えるでしょう。
PHEVはBEVとHEV両方の長所を兼ね備えています
PHEVはHEVと違って、大きな駆動用バッテリーを搭載しており、家庭でも充電することが可能です。
基本的にはバッテリーの電力を利用してモーターで駆動することが主体ですが、バッテリーの電力が少なくなれば、HEV同様にハイブリッドで走行が可能な構造になっています。
BEVとHEVの長所を兼ね備えていると言えるので、家庭でも充電したいがBEVの充電切れには不安がある方には、PHEVがおすすめです。
どちらも車体が重くなることがデメリットです
HEVとPHEVのどちらにも言えることですが、モーターやバッテリー以外にエンジンも搭載しているので、車体が重くなってしまうことがデメリットと言えるでしょう。
またPHEVはHEVに比べて、車両価格が割高になってしまうこと、一般的に車内が狭くなることも、デメリットとして挙げられます。
BEVとHEV、PHEVの特徴(まとめ)
今回はBEVとHEV、PHEVの特徴を中心に紹介してきましたが、それぞれにデメリットはありますが、それを上回る多くのメリットがありました。
テレビのCMでも温室効果ガスの排出量と吸収・除去量を均衡させる「カーボンニュートラル」が、キャッチフレーズのように使われる昨今です。
このように環境への関心が高まる中で、ガソリン車やディーゼル車からBEVやHEV、PHEV、FCEVなどへのシフトが、世界的にも急ピッチで進んでいます
充電設備などインフラ面での拡充、バッテリーの軽量化や長寿命化など、まだまだ整備や改善しなくてはいけない点もありますが、今後の国や自治体による整備やメーカーの技術革新に期待したいところです。
みなさんの愛車選びの際にこの記事が、少しでも参考にして戴ければと思います。