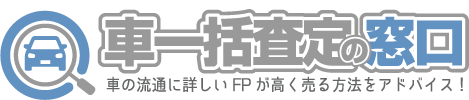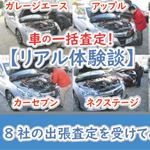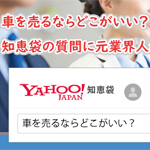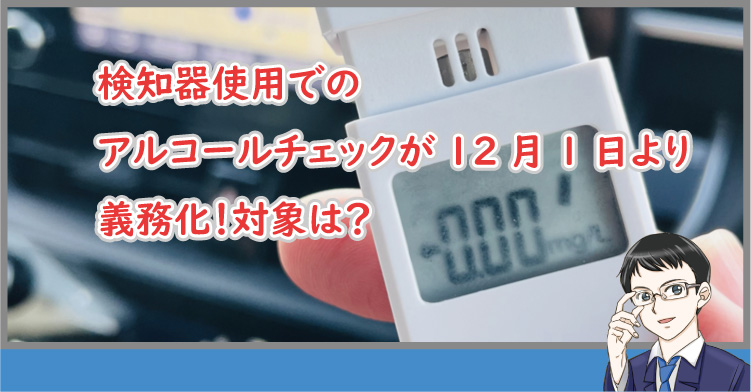
- 上京時に車はどうする?売却するべきかどうかの判断基準について - 2024年9月27日
- 車売却で契約後に査定額を勝手に減らす業者から身を守る簡単な方法 - 2024年9月19日
- MOTA車買取を使って2日のスピード売却に成功。デメリットは? - 2024年9月5日
罰則規定が厳しくなっても、なかなか減らないのが飲酒運転による事故です。
昨年4月より、一定数以上の車両を使用する白ナンバー事業者に対して、目視と点呼によるアルコールチェックが義務化されていますが、検知器使用でのアルコールチェックについても、2023年12月1日より義務化されることを発表しました。
既に旅客や運送業界など緑ナンバーの事業者については、検知器使用での検査が義務化されていますが、今回は白ナンバーの事業者にも義務化されることになります。
そこで今回は、検知器使用でのアルコールチェック義務化について、紹介していきましょう。
このページの目次
今回の義務化で、対象となる事業所とは?
業務で使用するクルマが対象
検知器使用によるアルコールチェック義務化の対象となるのは、送迎用マイクロバスなど定員11人以上の自家用自動車を1台以上使用、または自家用自動車を5台(原付は含まず二輪は0.5台換算)以上使用している、安全運転管理者の選任が必要な事業所となります。
ただし、該当するのは業務に使用する車両ですので、従業員個人所有で通勤用の車両は義務化の対象になりませんが、従業員所有の車両を業務で使用する際には対象となりますので注意が必要です。
安全運転管理者について
安全運転管理者は、上記で述べた一定台数以上の車両を使用する事業所において、運行の安全確保や交通法規の遵守をさせるために、選任が義務化されています。
また、20台以上の車両を使用している事業所では、20台につき1人の副安全運転管理者を選任することも必要です。
なお、安全運転管理者は20歳以上(副安全運転管理者をおく場合は30歳以上)で、運転管理者経験2年以上などの要件があり、選任後は15日以内に各都道府県の公安委員会に届け出書を提出する必要があります。
アルコールチェックで気をつけたいポイント
アルコールチェックはいつ行うのか
目視や点呼と同様に、検知器によるアルコールチェックは、業務による運転前と運転後に行う必要があります。
また、直行・直帰などで直接のチェックができない場合には、検知器を運転者に持たせるなどして、携帯電話のビデオ通話やクラウド管理などを使用して行うことも認められています。
チェックは安全運転管理者以外でも可能
アルコールチェックは、原則的に安全運転管理者が立会いで行う必要がありますが、不在の場合や対象人数が多い場合などには、副安全運転管理者または安全運転管理者の業務を補助する者(資格は不要)が行うことが可能です。
ただし、アルコールが検出された際には、ただちに安全運転管理者に報告して、必要な措置をとることが求められます。
チェックした記録について
アルコールチェックの記録を作成して、1年間保管しておくことが必要となりますが、書類の様式やパソコンでの保存ファイル形式の指定はありませんが、下記の事項について記録が必要となります。
- 確認者氏名
- 運転者氏名
- 自動車登録番号等
- 確認の日時
- アルコールチェックの方法(検知器使用の有無など)
- 酒気帯びの有無
- 指示事項
- その他必要な事項
罰則規定について
公安委員会から保存記録の提出を求められた際に、アルコールチェックを怠っていることや、記録がされていないことが判明すると、是正に必要な措置を求められることや安全運転管理者の解任を命じられることがあり、もし従わなかった場合には50万円以下の罰金刑となります。
また、安全運転管理者が選任されていない場合も、同じく50万円以下の罰金刑となりますのでご注意ください。
まとめ
今回は12月1日より義務化となる、検知器使用でのアルコールチェック義務化について、紹介いたしました。
業務中の飲酒運転事故は、運転者だけでなく事業所全体にも社会的に大きなペナルティが与えられることになり、事業所の経営や運営に大きなダメージを受けることも考えられます。
そのようなことを避けるためにも、アルコールチェックをはじめとした安全運転管理は、日頃からしっかりと行っていく必要があるといえるでしょう。
【参考】
● 安全運転管理者の業務の拡充等|警察庁Webサイト