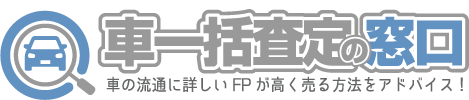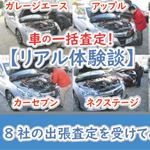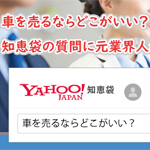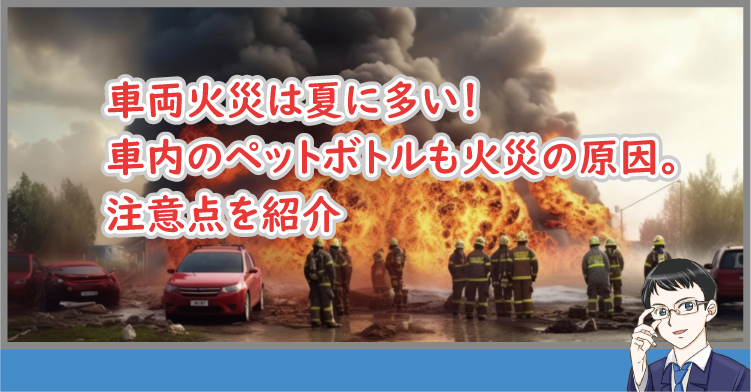
- 車の査定額を当日中に知りたい!最大20社の結果を簡単に知る方法 - 2024年7月23日
- MOTA車買取は当日中(最短3時間)に最大20社の査定額が分かる - 2024年7月22日
- SUV「ディフェンダーOCTA」は水深1MまでOK!発表の概要【たかまさ考察】 - 2024年7月8日
火災といえば、空気が乾燥する冬場に家屋が燃えることを連想する人が多いかもしれませんが、車両火災は家屋の火災と異なって、夏場に多く発生する傾向があるようです。
今年6月20日には千葉県内の国道357号線上で、購入した中古車を運転して帰宅途中のドライバーが、メーターに異常を感じて停車したところ出火して、全焼する車両火災が発生しました。
また、消防庁が2023年5月16日に発表した「令和4年(1月~12 月)における火災の概要」によると、昨年1年間に発生した車両火災は全国で3,414件と、1日あたりで約10件発生している計算になります。
今回は、夏場に多い車両火災について発生する原因や、注意すべき点を紹介いたします。
このページの目次
車両火災の原因で最も多いには排気管
消防庁の「令和4年(1月~12 月)における火災の概要」によると、昨年起きた車両火災3,414件の原因として、最も多かったのは排気管周辺からの出火で、595件(全体比17.4%)発生しました。
排気管がエンジンと接合する部分では、温度が300℃以上になることもあり、漏れたオイルや燃料などが付着することで発火する恐れがあります。
また、真夏にエアコンを効かせるために、エンジンをかけたままで停車していたところ、排気管の熱が原因で枯れ草に引火して火災が起きるケースも、過去には発生しているそうです。
気温が高い夏場はエンジンを切った後も、排気管の温度が下がりにくいので、草むらなどには駐車しないように気をつける必要があります。
電装品の取り付け不備も出火の原因に
配線のショートに注意
車両火災の出火原因として2番目に多かったのが、電装品の配線などを含む交通機関内配線で342件(全体比10.0%)発生しました。
配線がショートしてしまうものや、スパークによる引火など、カーナビやカーオーディオの取り付け不備が多いようですが、アース線がきちんと取られていないと出火の原因になってしまうこともあります。
電気機器からの出火も少なくない
次は3番目に多い出火原因として、電気機器によるもので280件(全体比8.2%)が発生しました。
こちらも配線と同様に、バッテリーがショートすることや、スパークによる引火、高温になることでの出火が原因で車両火災が発生することが多いようです。
発生件数は少なくても、とくに夏場は要注意
ペットボトルが原因で火災になったことも
真夏は水分補給をするためにペットボトルの飲料水などを、車内に持ち込むことが多くなります。
ところが飲料水の入ったペットボトルが凸レンズの役割を果たして、光を集めて出火する「収れん火災」を発生させた例が過去にはあるようです。
車両火災を防止するために、飲み残しが入ったペットボトルなどは、日の当たらない場所に収納しておくことが必要だといえます。
スマホやモバイルバッテリーの放置も危険
スマホやモバイルバッテリーにはリチウム電池が使用されていますが、リチウム電池が高温になると発火や破裂する危険性が高くなります。
特に気をつけたいのが、スマホをカーナビの代わりにするために、ホルダーなどでダッシュボード上に放置することです。
そのまま炎天下でエンジンを切って車を離れてしまうと、窓を閉め切ったダッシュボード上の温度は70℃を超えることもあり、たいへん危険な状態になります。
特に車内が高温になる夏場は、リチウム電池を使用した物を車内に放置しないように気をつけましょう。
まとめ
今回は夏場に多い車両火災の原因と、注意すべき点を紹介いたしました。
車両火災の原因としては排気管や電気系統が多く、高温になるエンジン自体が原因となるものは105件(全体比3.1%)と、意外にも少ないようです。
高温になる夏場は、車内に出火の原因となるものを置かない、駐車する際には燃えやすい物の上を避けるなど、車両火災を起こさないように気をつけたいものですね。
【参考】
● 消防統計(火災統計) | 総務省消防庁