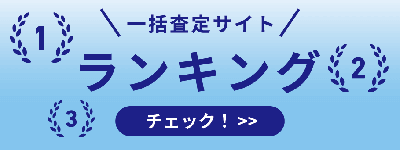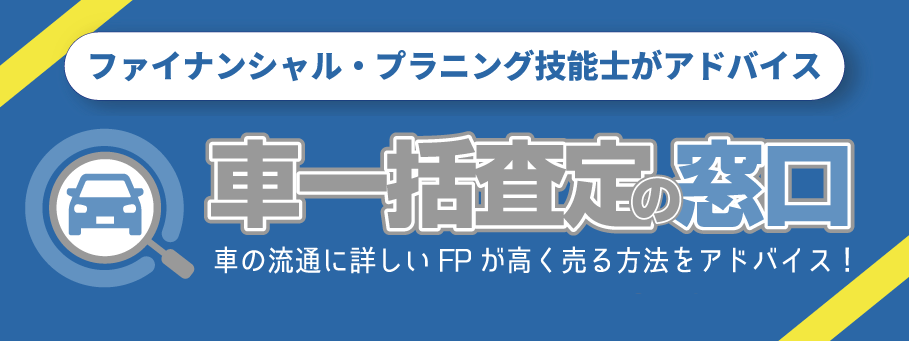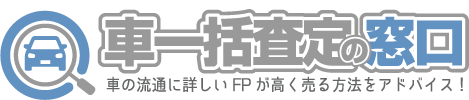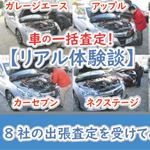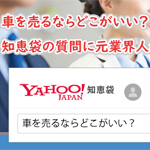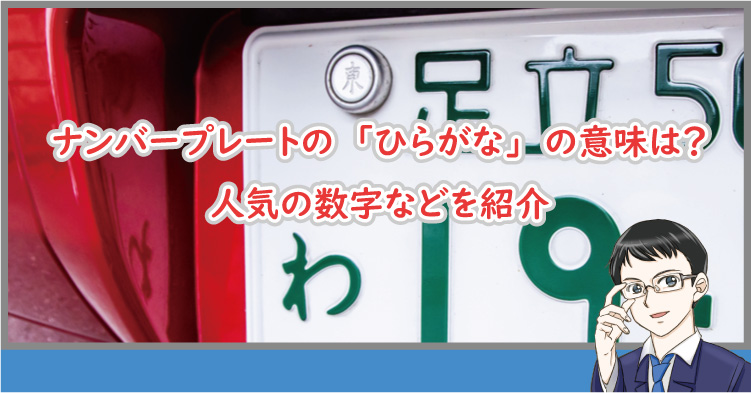
- 車の査定額を当日中に知りたい!最大20社の結果を簡単に知る方法 - 2024年7月23日
- MOTA車買取は当日中(最短3時間)に最大20社の査定額が分かる - 2024年7月22日
- SUV「ディフェンダーOCTA」は水深1MまでOK!発表の概要【たかまさ考察】 - 2024年7月8日
自動車では前後に装着されている、皆さんおなじみのナンバープレートですが、近年では図柄入りナンバーや希望ナンバー制度など、以前に比べると選択肢も増えてきました。
ナンバープレートの表示には、正式名称でいえば「地域名」、「分類番号(3桁の数字)」、「ひらがな」、「一連指定番号(4桁の数字)」の4つが表示されていますが、それぞれに分類するための規則や役割が与えられています。
今回は、ナンバープレートの歴史と、表示の区分の他に豆知識を紹介させていただきます。
このページの目次
ナンバープレートの歴史
日本に初めてナンバープレートが登場したのは、1907年の当時の東京府において警視庁が定めたものが始まりです。
当時の日本では交通ルールが確立されていなかったため事故が増えてしまい、車の所有者を明確にする必要があるために、4桁の数字を刻印したナンバープレートの装着が東京府内において義務づけられました。
1919年には全国で統一したものが義務付けられましたが、自家用車は黒地に白文字、営業車や特種自動車は白地に黒文字とされ、さらに地名を漢字の頭文字で表記したものであったそうです。
その後、1951年には都道府県名を表す漢字1文字に数字(分類番号)と車両ナンバーという形式が採用され、1955年にはひらがなが追加されて現在にかなり近い形式となり、1964年頃から地域名が現在と同じ2文字に変更されました。
また、1975年頃には、軽自動車は高速道路での最高速度が当時は時速80kmと制限されていたため、速度の遅い軽自動車をひと目で認識できるようにとの理由で、現在と同じ黄色地に黒文字のナンバープレートに変更されました。
分類番号とひらがなにも区分が存在します
分類番号は車種によって区分されています
基本的に3桁の数字で表示される分類番号ですが、1番先頭の数字は車種ごとに区分されています。
普通貨物自動車 1桁目:1
普通乗合自動車 1桁目:2
普通乗用自動車 1桁目:3
小型貨物自動車 1桁目:4または6
小型乗用自動車 1桁目:5または7
特種用途自動車 1桁目:8
大型特殊自動車 1桁目:9または0(建設機械用)
また10種類のアルファベット「A・C・F・H・K・L・M・P・X・Y」が、下2桁には使用可能です。
ひらがなの区分について
ひらがなについても区分がされていますが、軽自動車と軽自動車以外で異なります。
ちなみに「お」は「あ」と紛らわしい、「し」は縁起が悪い、「へ」は屁を連想させる、「ん」は発音しづらいために使用されていません。
軽自動車
事業用車両に「りれ」、レンタカーに「わ」、自家用車には「あいうえ」「かきくけこ」「さすせそ」「たちつてと」「なにぬねの」「はひふほ」「まみむめも」「やゆよ」「らるろ」「を」が使われています。
軽自動車以外の車両
事業用車両に「あいうえ」「かきくけこ」「を」、レンタカーには「われ」、自家用車には「さすせそ」「たちつてと」「なにぬねの」「はひふほ」「まみむめも」「やゆ」「らりるろ」が使われています。
ナンバープレートにまつわる話
希望ナンバー以外では使われない2桁の数字がある
4桁の一連指定番号は、希望ナンバー以外では連番で割り振られていきます。
その中でも、「42」と「49」が下2桁に使われない数字とされていますが、いずれも理由は公表されていませんが、縁起が悪いことが使われない理由のようです。
また、駐留軍人向けに限ってですが、「13」も欧米では縁起が悪いことから使われていません。
全国的に人気の数字は「1122」や「2525」など
希望ナンバー制の導入で、数字の語呂合わせから「1122(いい夫婦)」や「2525(にこにこ)」などが全国的に人気を集めています。
また最近は名古屋を中心に風水で運気が上がるとされる「358」や富士山ナンバーの富士山の標高にちなんだ「3776」、大阪ナンバーで「720」など、地域ごとに人気の番号もあるようです。
ナンバープレートで個人の特定がされてしまう?
普通乗用車など登録車の場合は、「登録事項等証明書」が所有者でなくても、誰でも発行することが可能となっています。
ただし、2007年の法改正によって、ナンバープレートの登録番号以外に車体番号も申請に必要となりました。
その他にも犯罪防止の観点から対策も講じられているので、現在では警察が事件性のある場合に調べる時などを除いて、個人の特定をされる可能性はかなり低いといえるでしょう。
また、軽自動車の場合は「検査記録事項等証明書」を請求することになりますが、所有者のみが請求可能になります。
ナンバープレートも進化する
今回はナンバープレートの歴史と、表示の区分の他に豆知識を紹介させていただきました。
身近なナンバープレートにも長い歴史があり、分類番号やひらがなにも区分や決まりがあることがおわかりいただけたかと思います。
1997年の希望ナンバー制度導入によって、自分の気に入った数字や記念日などを愛車のナンバープレートに付けられるようになったことは、車を購入する際の楽しみがひとつ増えたともいえるでしょう。
また図柄入りナンバーは今後も拡充されるようですので、その該当地域の人にとっては楽しみなことといえます。
車は性能だけでなく、ナンバープレートも時代に応じ進化していると言えるでしょう。
【参考】一般財団法人自動車検査登録情報協会