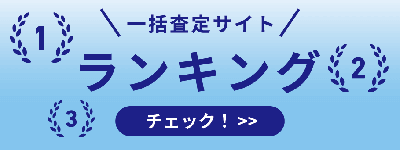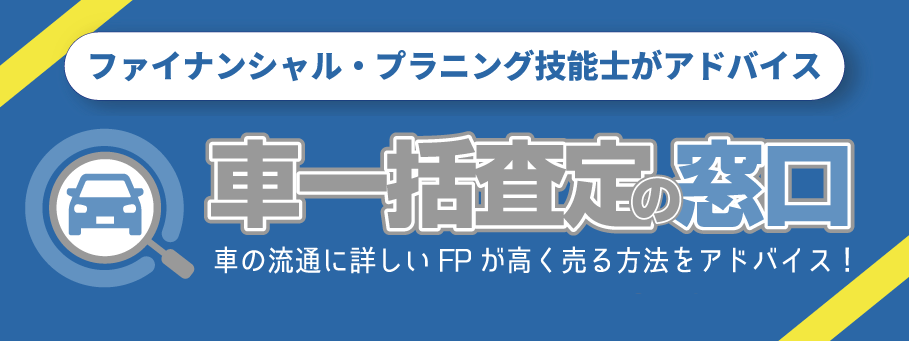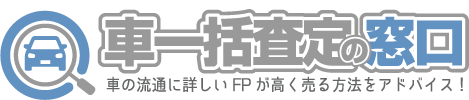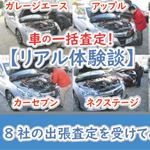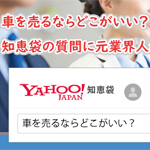- 車の査定額を当日中に知りたい!最大20社の結果を簡単に知る方法 - 2024年7月23日
- MOTA車買取は当日中(最短3時間)に最大20社の査定額が分かる - 2024年7月22日
- SUV「ディフェンダーOCTA」は水深1MまでOK!発表の概要【たかまさ考察】 - 2024年7月8日
自動車を購入しようとする際にメーカーのホームページやカタログなどで、スペック表(主要諸元表)でボディのサイズやエンジンの馬力などを調べられる方も多いかと思います。
スペック表には全長・全幅・全高などのサイズに加えて、最小回転半径など、車の取り回しに影響する情報にや、車両重量や燃費にエンジンの馬力など、その車種に関する数値が数多く記載されていますが、その数値は何を基準にして測定されているのか理解していないと、思わぬ落とし穴にはまる可能性もあるようです。
今回はスペック表に記載されている項目の中から、型式、ボディサイズに関するもの、車両の重量に関するものを中心に紹介いたします。
このページの目次
スペック表に記載されている型式とは?
スペック表にはアルファベットと数字を組み合わせた型式が記載されています。
この型式とは車検証にも記載されていますが、道路運送車両法に基づいて国土交通大臣が構造・装置・性能などが同一な自動車に対して指定した分類指標のことです。
型式をユーザーが使う機会はあまりありませんが、自動車保険に加入する際に記入することが必要な場合がある他に、車のパーツを自分で購入したりする場合には適合するかどうか調べる際に必要な場合があります。
ボディサイズと最小回転半径について
全長・全幅・全高について
全長は車両全体の長さを表す数値ですが、一般的にフロントバンパー最先端からリアバンパー最後部までの長さのことです。
ちなみに全長は軽自動車で3.4m以下、小型乗用車は4.7m以下と決められています。
次に全幅はボディの幅が一番広い部分の数値を表しますが、ドアミラーは含まれませんのでご注意ください。
また全幅は軽自動車で1.48m以下、小型自動車で1.7m以下と決められています。
続いて全高はタイヤの地面との接地面からボディの一番高い部分(通常はルーフ)までの高さを表しますが、可倒式や取り外し式のアンテナは倒した状態または取り外した状態、最初から装備されている固定式のアンテナやルーフレールは全高に含まれていますのでご注意ください。
なお全高は小型自動車で2.0m以下、軽自動車も2.0m以下と決められています。
ホイールベースと最低地上高について
ホイールベースは前輪の中心から後輪の中心までの長さを表します。
一般的にホイールベースが長いと、直進安定性が高くなることと、車内スペースを広くできるメリットがありますが、小回りが効きにくくなることがデメリットです。
次に最低地上高ですが、地面から自動車の一番低い部分までの高さを表しますが、マフラーやオイルパン、エアロパーツなど、車種によって一番低い部分は変わってきます。
トレッドについて
トレッドとは、左右のタイヤの中心間の幅を表すものですが、トレッドが大きいほどカーブでの安定性は増しますが、小回りが効かなくなるデメリットもあります。
なおトレッドは、前輪と後輪2カ所の数値が表示されることが一般的です。
最小回転半径について
ハンドルを最大限に切った状態で自動車を旋回させた時に、一番外側のタイヤの中心部分が描く円の半径が最小回転半径になります。
あまり知られていませんが、カタログに表記されている最小回転半径は、実際に自動車を走行させて測定した数値ではなく、あくまでも計算上での数値になりますので、実際の最小回転半径とは異なる場合もあるようです。
最小回転半径が小さいほど小回りが効きますので、自動車を選ぶ際に重要な数値のひとつといえるでしょう。
自動車の重量を表す数値と乗車定員について
車両重量について
車両重量はドライバーも含めて人を乗せていない状態で、燃料を満タンにしてオイルや冷却水なども規定量を入れた、すぐに走行できる状態での車両の重量を表示したものです(ただし、スペアタイヤや工具類などは含まれません)。
なお、乗用車の重量税(軽自動車は除く)の税額は、車両重量をもとに算出されます。
車両総重量について
乗用車の場合には、車両重量に最大乗車定員分の重量を加えた数値が車両総重量になります。
また乗員は1名あたり55kgで計算されますので、定員5人の乗用車では車両重量+55kg×5の数値が車両総重量です。
なお1ナンバーや4ナンバーの貨物車の場合は、さらに最大積載量が加えた数値が車両総重量になります。
乗車定員について
軽乗用車では4名、一般的な普通乗用車では4~8名と車種によって違いますが、乗車定員を超える人を乗せて走行させると「定員外乗車違反」になります。
なお、12歳未満の子供については3人で、12歳以上の大人2人の扱いになりますので注意が必要です。
また乗車定員はあくまでも法的に乗車することが可能な上限ですので、中には乗車定員いっぱいに人が乗ると荷物を入れるスペースがなくなってしまう車種もあります。
自動車を購入する際には、実際に現車をしっかり確認することをおすすめします。
まとめ
今回はカタログなどのスペック表に記載されている項目の中から、型式、ボディサイズに関するもの、車両の重量に関するものを中心に紹介いたしました。
自動車のスペック表では、つい燃費やエンジン出力などに目が奪われがちですが、全長・全幅・全高のサイズや最小回転半径は自動車の使い勝手に影響する重要なファクターです。
今回の記事が自動車の購入を検討する際に、少しでも参考になればと思います。
【参考】
● 最小半径|国土交通省