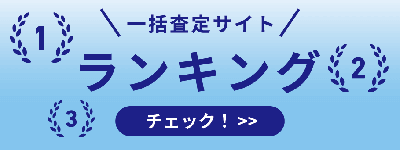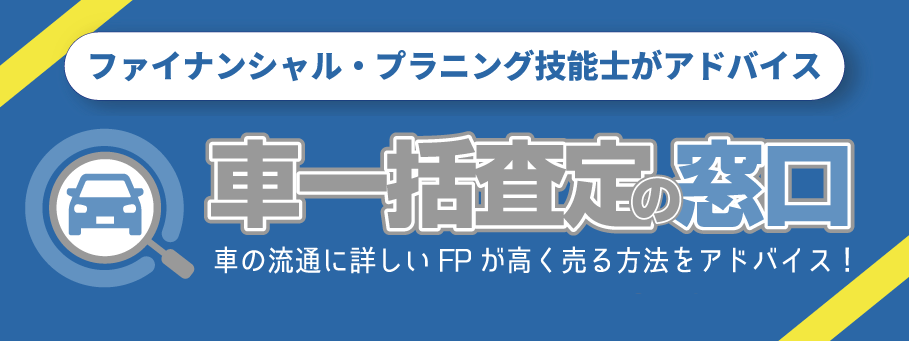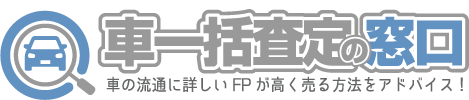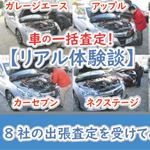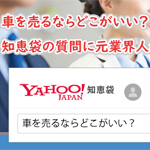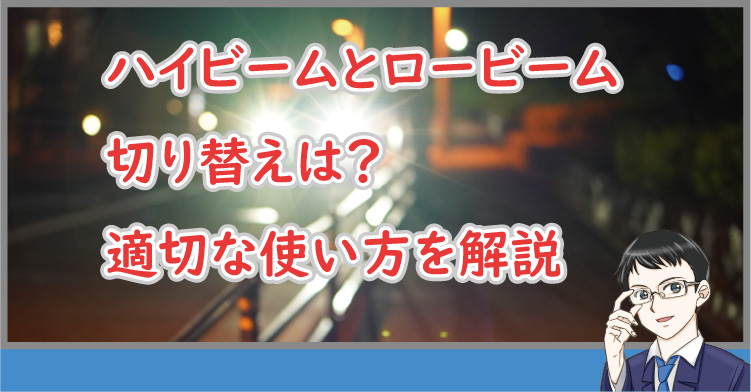
- 車の査定額を当日中に知りたい!最大20社の結果を簡単に知る方法 - 2024年7月23日
- MOTA車買取は当日中(最短3時間)に最大20社の査定額が分かる - 2024年7月22日
- SUV「ディフェンダーOCTA」は水深1MまでOK!発表の概要【たかまさ考察】 - 2024年7月8日
みなさんご存じのように、車のヘッドライトには上向きのハイビームと下向きのロービームの切替えがあります。
市街地を走行していると、ハイビームのままで走行している対向車に、眩しいと思った経験があるドライバーも多いのではないでしょうか?
一方で、対向車もいない暗い夜道をロービームで走行しつづけるドライバーも、けっして少なくありません。
ハイビームとロービームの切替えは、曖昧(あいまい)になっているのが現状のようですが、最近では基本的にはハイビームを使うことを推奨する動きも、出てきています。
今回はハイビームとロービームのどちらを使うのが正解なのか、JAF(一般社団法人日本自動車連盟)のユーザーテストの結果もまじえて解説いたします。
このページの目次
ハイビームとロービームの切替えを法的観点から考えてみましょう
道路運送車両法では、ヘッドライトのハイビームは「走行用前照灯」と呼ばれ、前方100mを視認できなければならないと決められています。
一方でロービームは「すれ違い用前照灯」と呼ばれ、前方40mを視認できることが必要です。
このように、道路運送車両法の観点からみてみると、ハイビームが通常走行時に使用することがわかります。
また、道路交通法第52条第2項では、
「車両等が、夜間、他の車両等と行き違う場合または他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げる恐れがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない」
と定められていることから、こちらではすれ違い時や前走車がいる場合には、ロービームを使用することが定められているようです。
このように、法的観点からみてみると通常走行時はハイビーム、すれ違いや前走車がいるときにはロービームの使用が正解といえるでしょう。
ハイビームとロービームの比較テストの結果には驚きの差が発生しました
こちらではJAFが行ったユーザーテスト、「見えない!止まれない!ロービームの限界を知る」の結果を紹介させていただきます。
こちらのテストは5人のドライバーが、それぞれテストコース内を時速80kmと時速100km(ロービームのみ)で周回して、コース上に設置した障害物の手前でブレーキのみで停止できるか、ハイビームとロービームの違いで検証したものです。
ハイビームでは余裕をもって停止できました
時速80kmのハイビーム走行のテストでは、障害物に1番近づいて停止したドライバーで44m手前、1番離れて停止できたドライバーでは111m手前となっており、5人の平均値は82m手前と余裕をもって停止することができました。
ロービームの時速100kmでは止まれないドライバーも
時速80kmのロービーム走行のテストでは、障害物に1番近づいて停止したドライバーで1m手前、1番離れて停止できたドライバーでも15m手前となっており、5人の平均値は5.6m手前と余裕があるとは決していえない結果となりました。
今回はテストのため、あらかじめ障害物の存在をドライバーが知っていましたが、人や障害物が急に現れる通常の一般道走行では、これ以上に停止距離が延びることも十分に考えられます。
つぎに時速100kmでのテストはロービームでしか行われませんでしたが、障害物手前で停止できたドライバーは1m手前で停止した1人のみ、残りの4人は障害物を通り越した1m~13m先と、実際の道路で人や自転車であれば、大惨事になる可能性も高い結果となりました。
今回のテストから、ロービームを使用した走行ではハイビーム使用時に比べると、暗い夜道で人や障害物の発見が大幅に遅れることがおわかりいただけたでしょう。
ハイビームとロービームを使い分けましょう!
ハイビームを使うシチュエーション
警察庁の調査によると、夜間に発生したクルマと自転車との事故のうち約56%の事故で衝突回避ができた可能性が高いことが判明しています。
少しでも早く歩行者や自転車をいち早く発見するためにも、前走車や対向車、対向する歩行者などがいない場合には、遠くまで視界が確保できるハイビームを使用することが、安全を確保するための基本だといえるでしょう。
ロービームを使うシチュエーション
一方で雨降りや降雪、霧などの際にハイビームを点灯させると、空気中の水滴に光が乱反射してしまい、かえって視界を妨げてしまい危険性が高まってしまいます。
このように天候の悪い時には、ハイビームではなくロービームを点灯させることが基本といえるでしょう。
また、自車の存在を他車に知らせるためにも、昼間でもロービームの点灯をすることが必要です。
まとめ
今回はハイビームとロービームのどちらを使うのが正解なのか、JAFのユーザーテストの結果、ハイビームとロービームのシチュエーション別による使用について、解説させていただきました。
かなり前のデーターにはなりますが警察庁による、2015年度に横断歩道を夜間に歩行中の歩行者が車にはねられて死亡する事故のうち、96%の車がロービームを使用していたそうです。
事故を未然に防ぐためにも、ハイビームとロービームを積極的に使い分けることが必要だといえるでしょう。
【参考】
● JAF(一般社団法人日本自動車連盟)ユーザーテスト「見えない!止まれない!ロービームの限界を知る」」