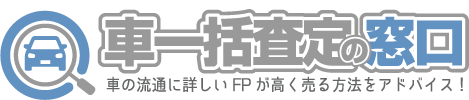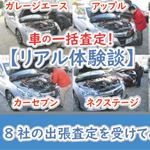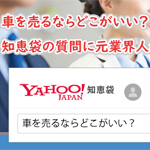- ユーザー車検で車検費用を節約!メリットとデメリットを解説 - 2024年4月23日
- ETCの通勤パスとは?ETC割引の社会実験が複数の地域で開始 - 2024年4月22日
- 初めて選んだ車種は?はじめてのマイカーに関する調査を紹介 - 2024年4月15日
飲酒運転の罪は道路交通法のなかでも非常に重く、極めて悪質な行為だとされています。
自動車や自転車で飲酒運転をすると取り締まりの対象です。しかし、自動車の場合の飲酒運転の違反と自転車の場合とでは同じ違反であっても定義等が異なります。
また、自転車で飲酒運転で検挙された場合であっても、当該者が運転免許を取得していた場合は、免許を取り消される可能性もあります。
今回は実際にどのような行為が違反になるのかについて解説します。
飲酒運転とは
飲酒運転は、少しでもアルコール分を含んだ食べ物や飲み物を食べたり飲んだりした状態で、車を運転したら即アウトというわけではありません。
違反となる呼気中のアルコール濃度が決められていて、その基準に基づいて法律は決まっています。
飲酒運転には酒気帯び運転と酒酔い運転の2つのパターンがあります。
酒気帯び運転とは、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上検出された状態のことです。
酒酔い運転とは、明らかに酔っている状態のことです。呼気中アルコール濃度はアルコールに強い体質であったとしても関係ないので注意が必要です。
お酒を飲んで自転車に乗るとどうなるのか
飲酒運転では酒気帯び運転と酒酔い運転の2つがあります。
実は自動車と自転車では飲酒運転に罰則が同じではありません。
道路交通法第117条で「酒気帯び運転」についての条文に「軽車両を除く」と書かれています。
つまり自動車の場合はどちらの状態であったとしても違反になりますが、自転車の場合だと酒酔い運転のみ取り締まりの対象となります。
酒酔い運転は、呼気中アルコール濃度が定められていなです。そのため運転者の状態を見て判断されます。
例えばまっすぐに歩くことができるか、まともに会話できるかなどのテストを行い酒酔い運転か判断されます。
もし自転車にアルコールを飲んだ状態で乗る場合、アルコールに弱い体質だと少量の飲酒であったとしても酒酔い運転とみなされるかもしれません。
自転車で飲酒運転をした場合に捕まると、自動車の運転免許はどうなるのか気になる人もいるのではないでしょうか。
道交法103条で「運転免許を受けた者が著しく交通の危険を生じさせる恐れがあるときは、6カ月を超えない範囲で免許の効力を停止することができる」と書かれています。
そのため違反したのが自転車であったとしても免停を受ける可能性は十分にあります。
自転車の場合は飲酒していても、酒酔い運転でなかったら捕まらないからといって飲酒運転してもいいわけではありません。
自分では気づかないうちに酔っているかもしれません。飲酒したら自転車にも乗らないのが一番です。
飲酒運転は絶対にダメ!
飲酒運転は道路交通法のなかでも違反の罰則が重い法律のひとつです。
飲酒運転を防ぐためには運転者だけが気を付けなければならないわけではありません。一緒に飲んでいた人やお酒を提供するお店、家族など、みんなで防ぐ姿勢が大事だと思います。
タクシーで帰ったり、代行運転を頼んだりすると、費用がかかるので躊躇しがちですが、それを怠った代償は、一生かかっても償えないほどの重大なものになります。
バレるバレないの問題ではないことを肝に銘じ、免許を持つ者としての責任を自覚して欲しいです。