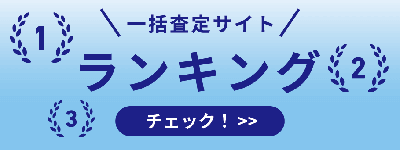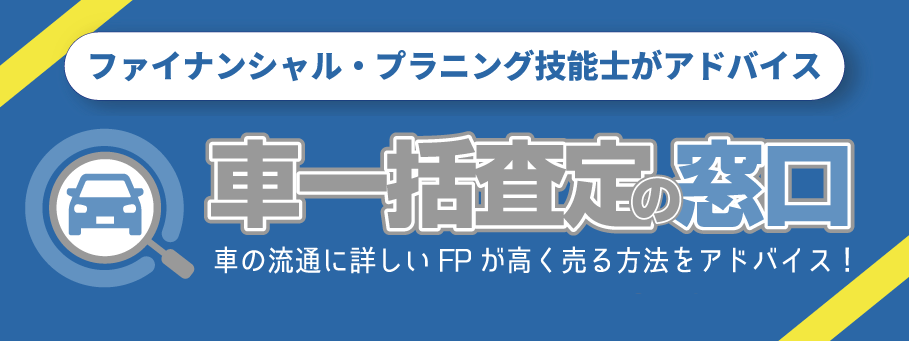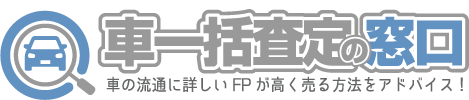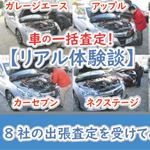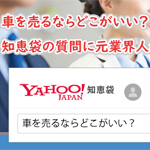- 憧れの名車に出会える!おすすめの自動車博物館を紹介 - 2024年5月8日
- カローラフィールダーが安いのは理由がある!シエンタとも比較してみた - 2024年4月29日
- ユーザー車検で車検費用を節約!メリットとデメリットを解説 - 2024年4月23日
ご存じのようにシートベルトは、事故の際に乗員の車外への放出を防ぐこと以外にも、ハンドルやフロントガラスなどへの衝突を防ぐ、大切な役割を担っている安全装備です。
現代では負傷や妊娠中などの例外を除けば、乗用車では全ての座席でシートベルトの着用が義務化されていますが、2021年にJAF(一般社団法人日本自動車連盟)が行った調査では、後部座席での着用は一般道路で42.9%、高速道路で75.7%とまだまだ低い着用率となっています。
そして、後部座席のベルト未着用は、前席にも重大な影響を及ぼすことが分かっています。
今回はシートベルトについて、その歴史や性能、非装着時の事故時の危険性などを紹介いたします。
シートベルトの歴史は意外と古かった
シートベルトの歴史は古く、1903年にフランスの技術者によって、高い背もたれと交差式ベルトからなる「自動車等の防御用ベルト」というものが考案されて、これがシートベルトの原型といわれています。
現代の3点式シートベルトは、1959年にボルボのエンジニアによって発明されましたが、それ以前からある腰部分のみをホールドする2点式に比べて、胸部や頭部の負傷リスクを大幅に下げる画期的な発明でした。
一方で日本では交通事故の死者が年々増えていたことから、シートベルトを全ての新車への装備が1969年に義務付けられましたが、1985年には高速道路や自動車専用道路で運転席と助手席での着用が義務化されます。
その後、1992年には一般道路も運転席と助手席でのシートベルト着用が義務化されますが、後部座席を含む全席でのシートベルト着用が義務化されたのは2008年のことです。
シートベルトの強度や材質、構造について
シートベルトには恐るべき強度があります
事故時の衝撃は一瞬とはいえ、すさまじいものです。
そのため、シートベルトの破壊強度はJIS規格で、肩ウェビング=1810kgf(重量キログラム)以上、腰ウェビング=2720kgf以上と定められています。
わかりやすく説明しますと、シートベルトを使って乗用車1台を引っ張ることができるだけの強度があります。
その他には、シートベルトと車のボディをつなぐ金具などに、強度が高いクロムモリブデン鋼などが使われており、事故の衝撃でも破損しないような強度が確保されています。
ベルトの素材はポリエステルが主流に
以前はシートベルトの素材としてポリアミド(ナイロン)が用いられてきましたが、最近ではポリエステル素材を幾重にも織り込んで、頑丈にしたものが主流になっています。
また、一定以上の力が加わることで素材が伸びるようになっており、衝撃を受けた際の人体への負担を軽減する工夫もされているようです。
シートベルトの構造も進化しています
現代のほとんどの3点式シートベルトは、ゆっくりと引っ張ればベルトがスムーズに引き出せますが、急激に引っ張るとロックして引き出せなくなる「ELR(Emergency Locking Retractor/非常時固定及び巻き取り式)」が採用されています。
この「ELR」が作動することで、事故時に乗員をしっかりと拘束することができるのですが、それに加えて車が衝突などで衝撃を受けた時には、火薬などで瞬時にシートベルトを自動的に巻き取る「プリテンショナー機能」も搭載されており、衝撃による乗員の移動を減らすことで安全性が高められているのです。
また最近では、衝撃の大きさによってシートベルトの拘束力をコントロールできる、「ロードリミッター」も取り入れられています。
後席のシートベルト非装着は前席にも危険が及びます
ここではJAFが以前に行った、後部座席のシートベルト装着時と非装着時のテスト結果を紹介いたします。
シートベルト着用と非着用で大きな差が発生
今回のテストではミニバンにダミー人形を前席と後部座席に2体ずつ乗せて、後部座席運転者側のみシートベルト非着用として、時速55㎞でのフルラップ前面衝突にて行われました。
テストの結果は、シートベルト非着用の後部座席ダミーは、衝突時に前方に投げ出されて、ヘッドレストを介して運転席ダミーの頭部を押しつぶし、衝撃を表す数値は後部座席ダミーでHIC2192、運転席のダミーもHIC1171まで上昇しました。
なお、シートベルトを装着していた後部座席ダミーは、シートベルトでしっかり固定されていたため、前方に投げ出されることはありませんでした。
HIC数値が表す意味は?
HICとは聞き慣れないことばですが、衝突や落下などの衝撃が原因による、脳や頭蓋骨への損傷程度を表す数値のことです。
ちなみに、脳しんとうを引き起こす衝撃レベルはHIC1000、死亡や重傷につながる致命的な頭部損傷を負う危険性がある衝撃レベルがHIC2000といわれていますので、衝突時においてシートベルト非着用の危険性が、おわかりいただけるでしょう。
まとめ
今回は事故の際に乗員を守るシートベルトについて、その歴史や性能、非装着時の事故時の危険性などを紹介いたしました。
ご紹介しましたJAFのテスト結果からも、後部座席の乗員がシートベルトを着用しないことで、前席の乗員にまで致命的な負傷させる可能性があることを、おわかりいただけたかと思います。
車の安全技術は年々進歩していますが、事故を100%防げるものではありません。
シートベルトは乗員の身を守るための基本ですので、後部座席の乗員も必ず装着しましょう。
【参考】
● JAF(一般社団法人日本自動車連盟)「後席シートベルト非着用時の危険性(ユーザーテスト)」